中学受験において過去問演習は、必要不可欠と言ってもいいくらい重要なものです。過去問をとおして、自分の志望する学校がどのような生徒を求めているかを知ることができるからです。過去問演習をいつから始めるべきかは、よく考えて学習を進めていきましょう。
過去問をは9月頃に始めるのがよい
過去問はどこで手に入れることができるのか
過去問に取り組むときの4つのポイント
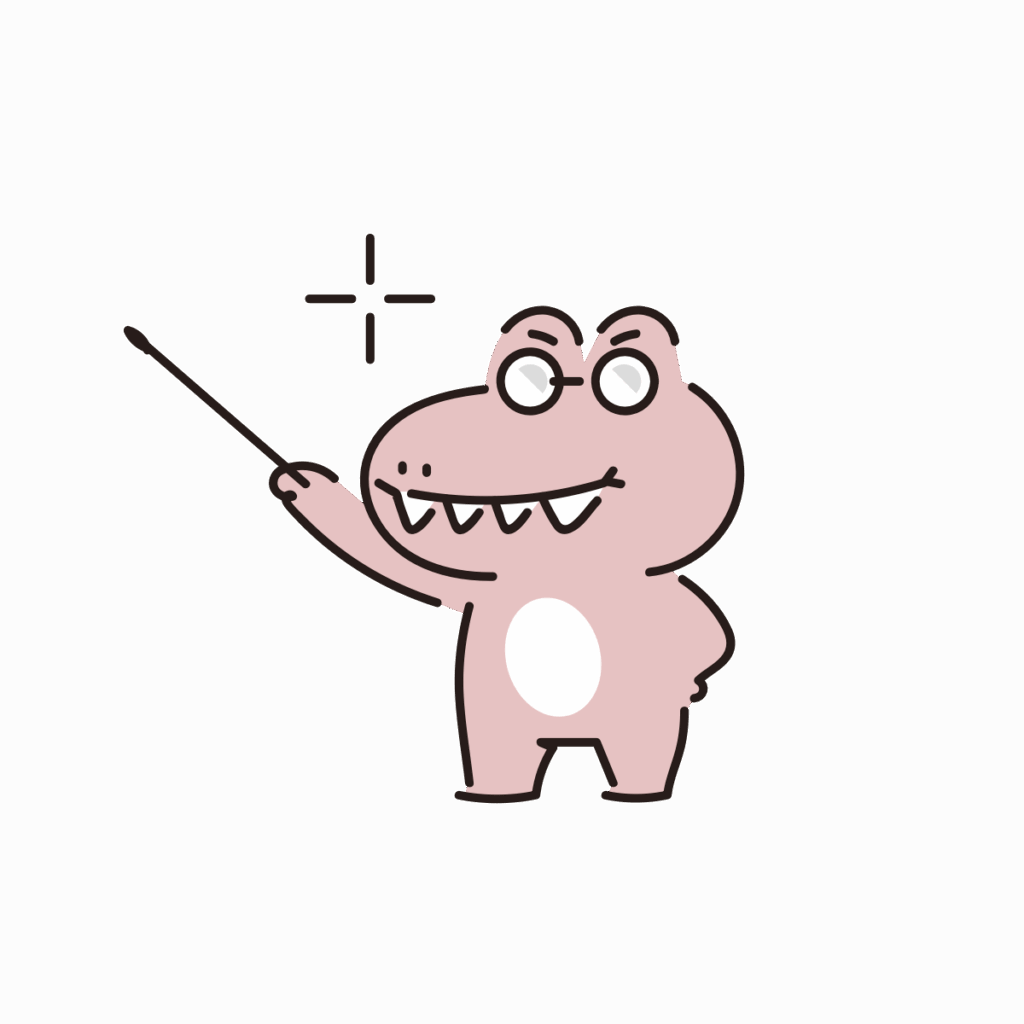
過去問演習を始める時期
過去問を始める時期についてはさまざまな考えからがありますが、夏休み後の9月、遅くても10月に始めるのがおすすめです。
9月から始める理由
9月から始める理由は、ほとんどの塾では夏休みで中学受験の基礎固めが終わるということです。ここから受験本番まで約5ヶ月になります。
たとえば第1志望を5年分×2周、第2志望を3年分×1周、第3志望校2年分を1周だとして、全部で15年分ほどの過去問を解くことになります。1週間に1年分解くと約4ヶ月かかるので、年末までに一通り終わる感じになるでしょう。受験校が3校だけという受験生は少ないと思うので、実際にはそれ以上になることもあるかもしれません。

わが子たちも、1週間に1年分ペースで進めていきました。祝日などで学校のお休みの時にはプラスして取り組みました。
早すぎても遅ずぎてもよくない
早めに始めた方がたくさんの過去問に取り組めるという面もあります。ですが、基礎が固まっていないうちに取り組むと解けない問題が多く、せっかくの過去問を無駄にしてしまうことになります。また解けない問題が多くて、自信をなくしてしまうこともあります。
逆に遅すぎると、出題傾向の把握や苦手単元の補強などができず志望校対策が不十分になってしまいます。塾から過去問についての指示がある場合もあるので、確認しておきましょう。
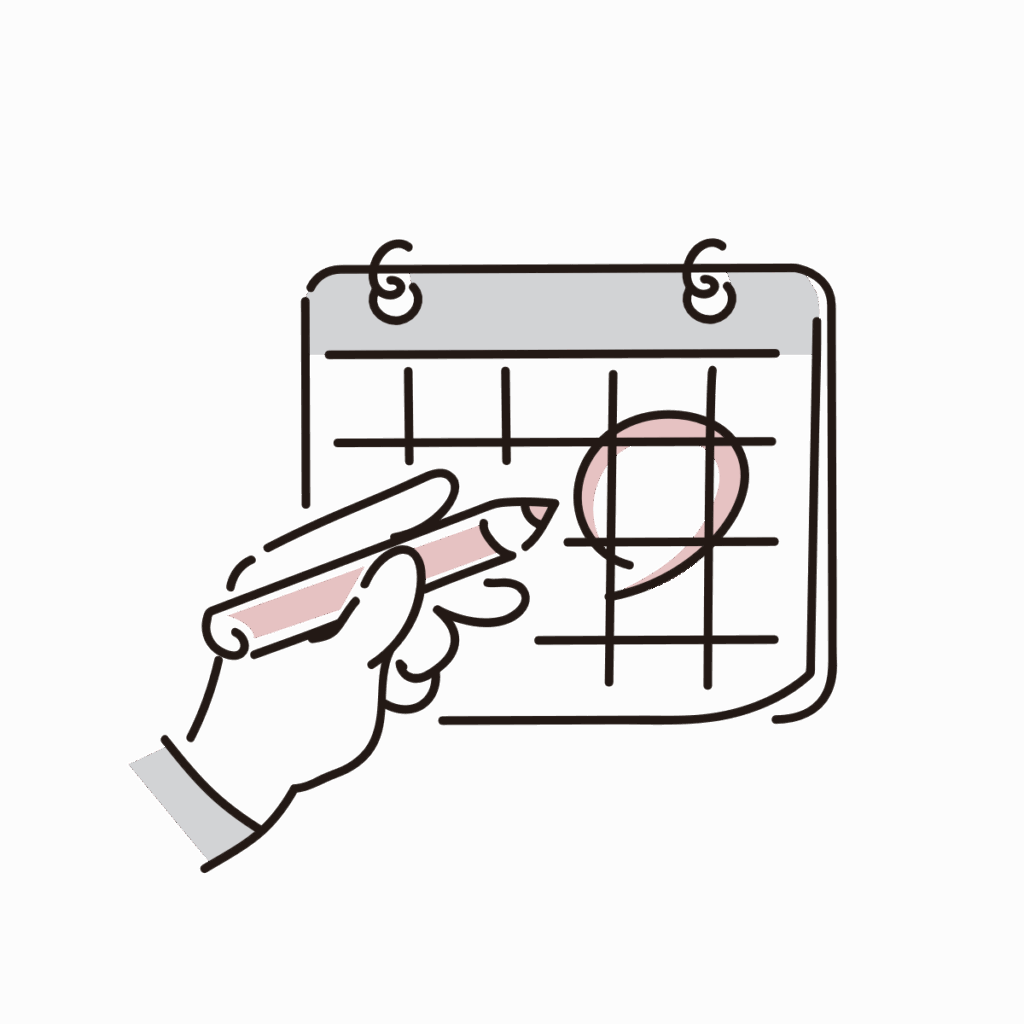
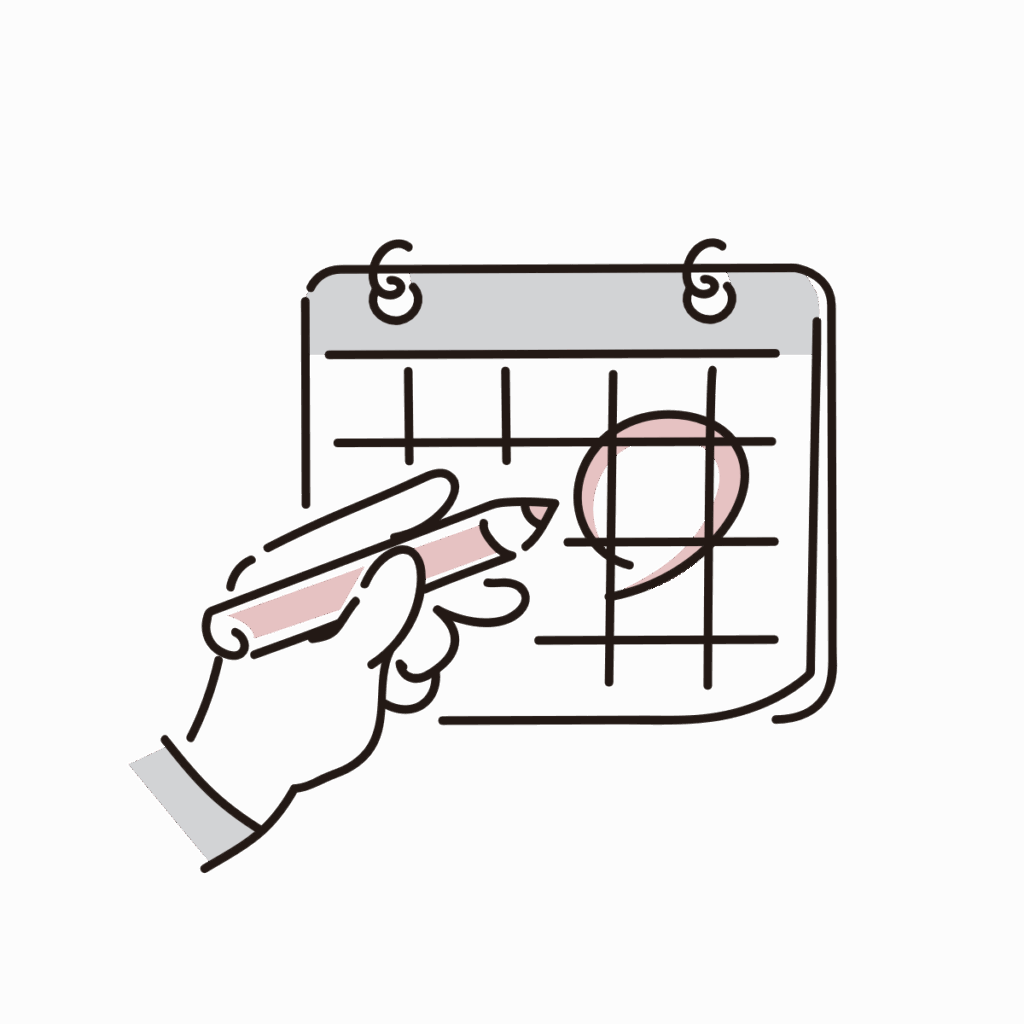
過去問はどこで手に入れる?
| 入手場所 | 時期 | 備考 |
|---|---|---|
| 市販の過去問題集 | 3月下旬から7月中旬 | 書店やネットで購入 塾で購入できることもある |
| 学校のHP | 3月頃から | 学校によっては直近の年度分をPDFでダウンロードできることがある |
| 学校説明会 | 4月から秋頃 | 参加者に無料または有料配布していることがある |
前年度のものなら古本屋やフリマでも扱っていることもありますが、学校によって問題の形式や傾向が変わっている場合もあります。志望度が高い学校はできるだけ最新のものを用意した方がよいでしょう。



大問1に出題されていた漢字が大問4出題されていただけでも、本番では戸惑うものです。
四谷大塚や日能研のサイト、「日本の学校」のサイトでもダウンロードできるものもありますが、国語の問題が掲載されていなかったり解答がないことがあります。印刷のしやすさや、お試しで問題を見てみるという点でメリットがありますが、過去問題集も必要なります・
声の教育社か東京学参か
いわゆる赤本といわれる過去問題集の出版社はいくつかありますが、声の教育者と東京学参が有名です。取扱のある学校や収録年数な度に違いがあります。私としては、声の教育社は解説が詳しく国語の問題の掲載数が多い、東京学参は問題の難易度が分析されていて収録年数が多いイメージです。どちらの問題集も、メリットデメリットがありますので、できる限り書店等で中身を確認してお子さんに合ったものを購入しましょう。
丸善の過去問題集一覧だと、出版社と収録年数がわかりすいのでリンクを貼っておきます。
過去問に取り組む時のポイント
過去問はコピーする
コピーをする理由は2つあります。
1つめは、問題を解く時に印をつけたり図に書き込むので、過去問題集に直接書き込むと2回目に解く時にやりづらくなってしまうからです。
もう1つの理由は、本番と同じ形式で解きたいからです。過去問題集を開いてみるとわかるのですが、製本上文字が小さいですし、見開きのページの片方に他の教科の回答が載っていたりもします。また、本に厚さがあって子どもには扱いづらい面もあります。解答用紙の欄も小さくなっているので、字の大きさによって文字数がかなり変わってしまいます。ちょっと面倒ですが問題用紙と解答用紙はコピーします。



解答用紙がされている場合は、指定されたサイズに拡大します。
私はコンビニでコピーしていました。これがかなり大変💦1枚ずつめくってコピーしていくのですが枚数もさることながら、厚みがあって本の綴じている部分がうまくコピーできない。延々と続くこの作業をやっていると、他にコピー機を使いたい人がきて譲ったりするのでなかなか終わらない…赤本はカラーも鮮やかですし、学校名も目立ちます。近くのコンビニは知り合いも利用することもあるので、あえて学区外のコンビニを利用したりもしました。中には業者にコピーを依頼する人もいます。



A3サイズの解答用紙が多いので、家庭にA3サイズのコピー機があると便利です。
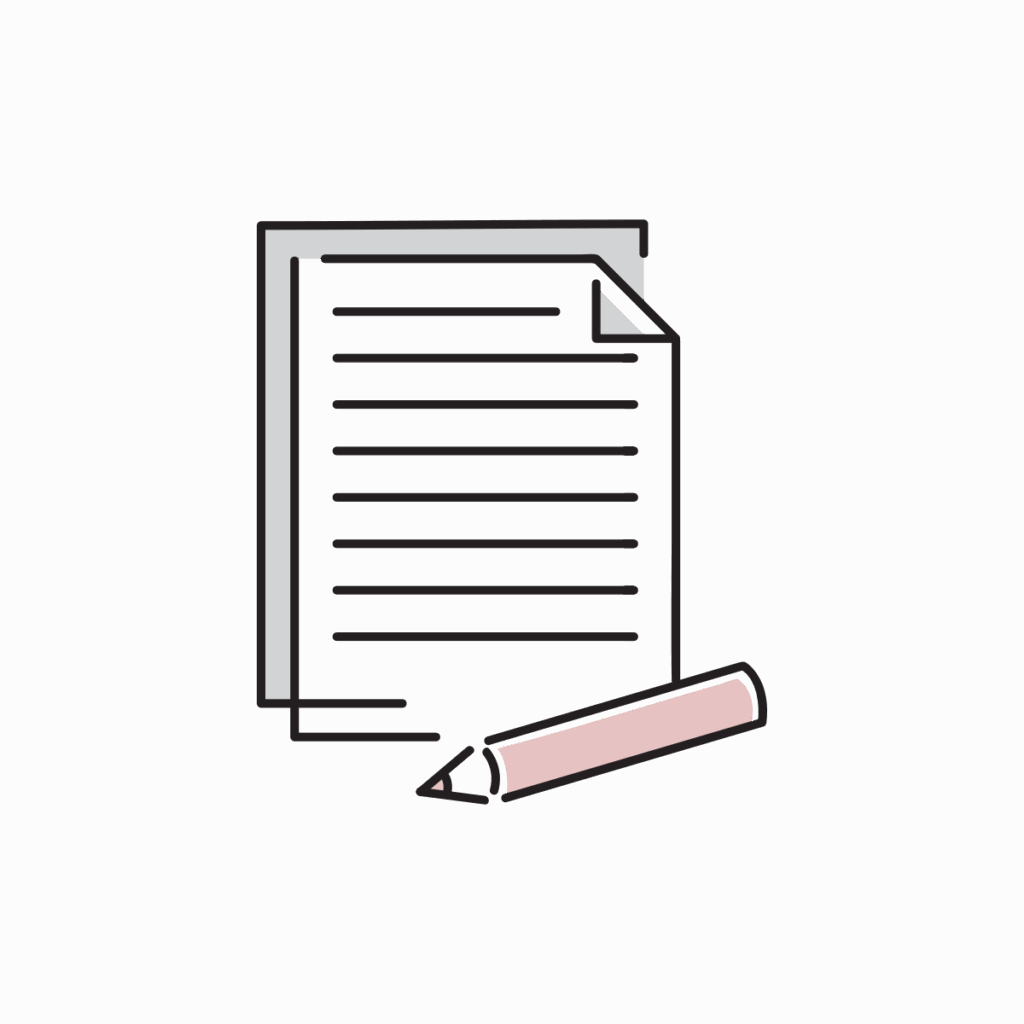
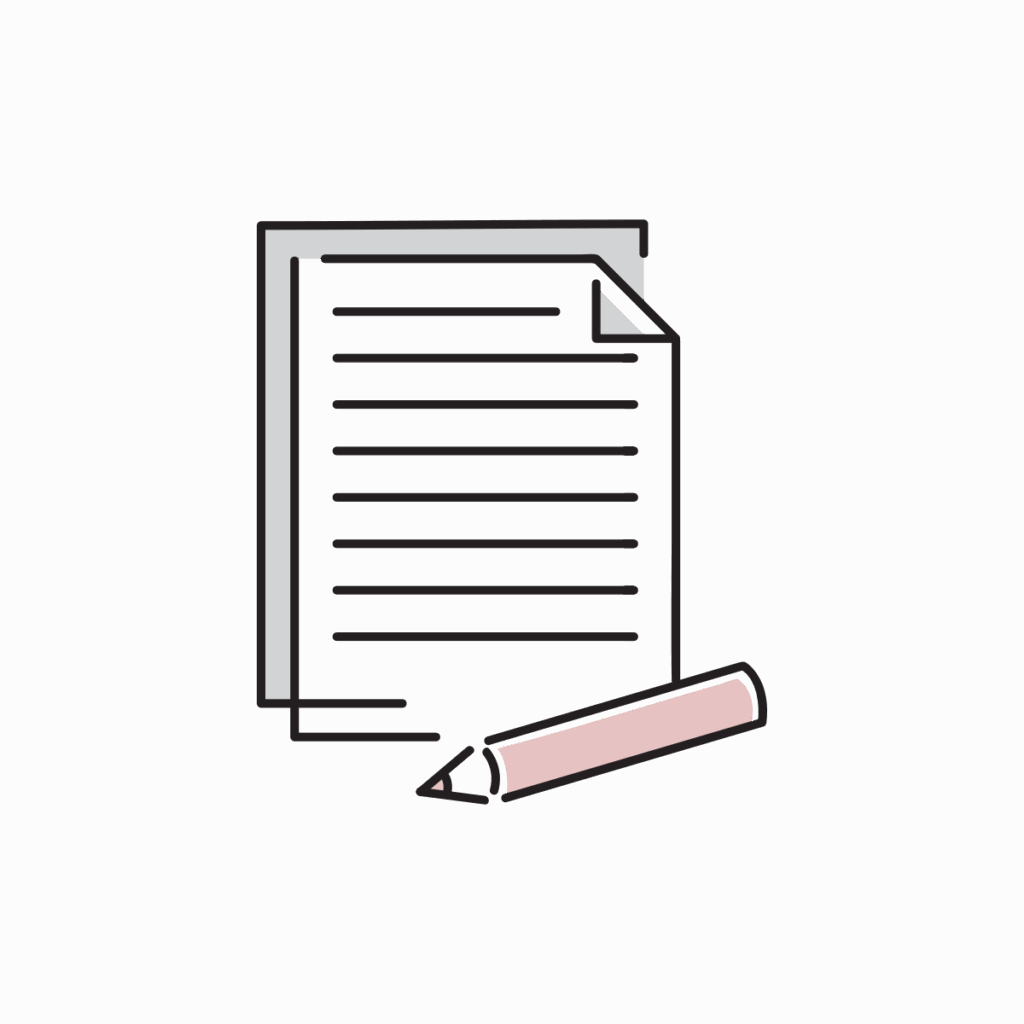
時間を測る
時間を測って本番と同じ形式で取り組むことで、時間配分を考えたりどの問題から解いてどの問題を後回しにするか判断する練習をしていきます。本番では満点をとるのではなく、解ける問題をしっかり解いてくることが大切になってきます。過去問で得点の仕方の演習を、積んでいきます。
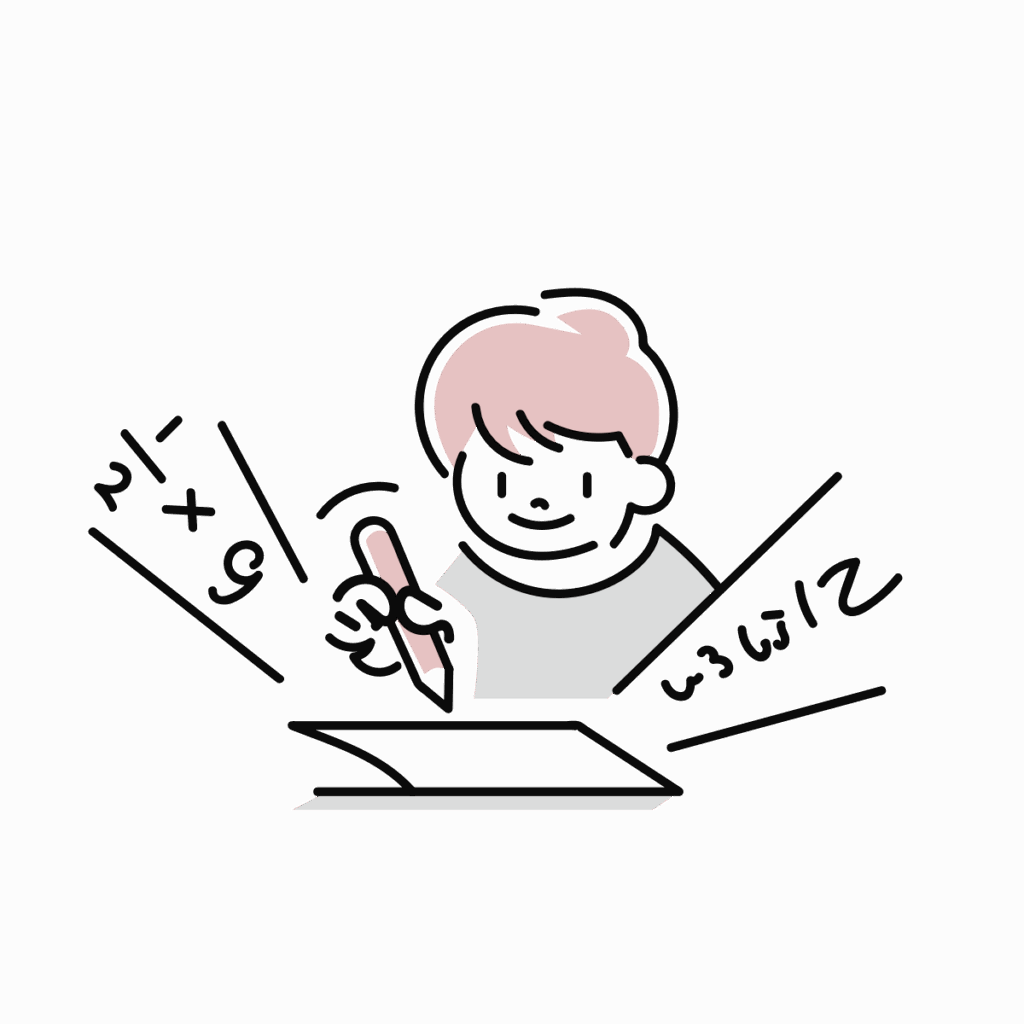
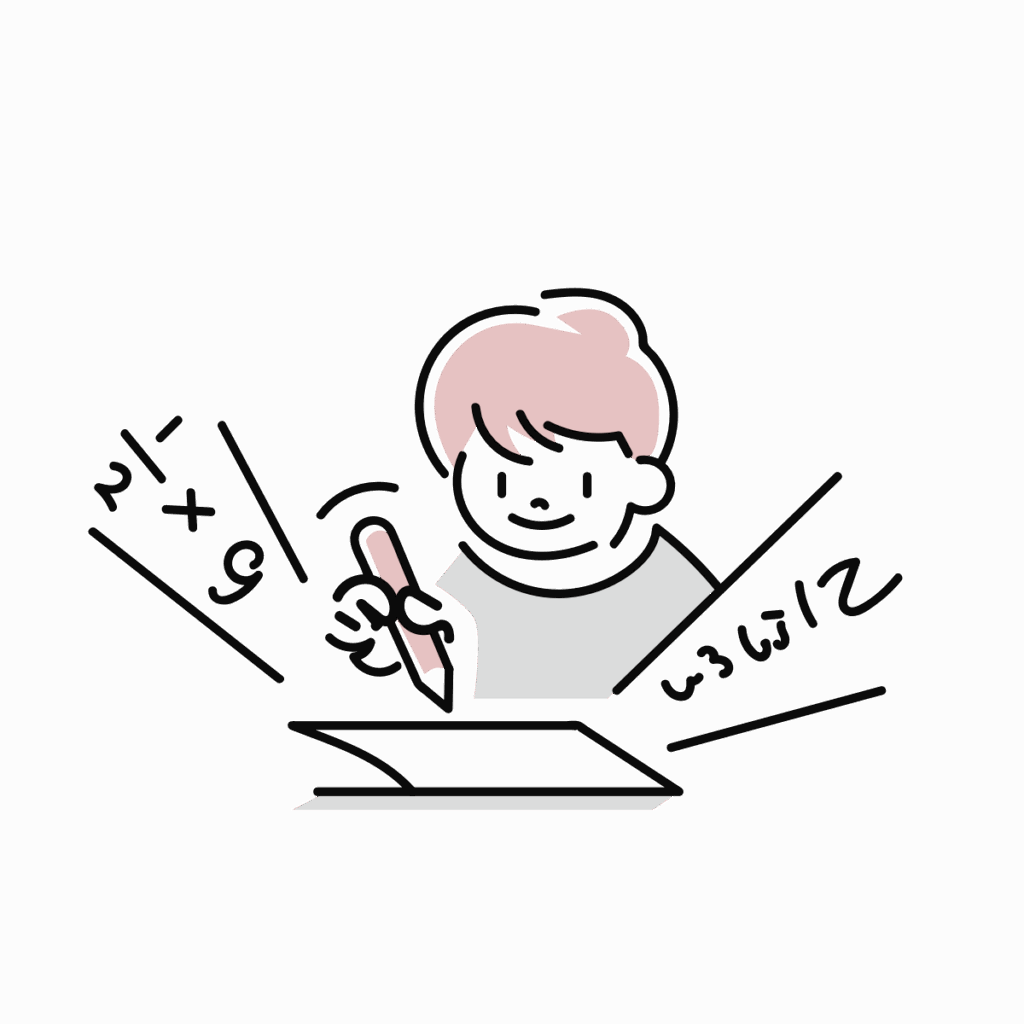
合格最低点や平均点にこだわらない
過去問の点数が良くないと悩む保護者の方がよくいます。合格最低点や平均点は、受験本番の際のデータです。そのため、過去問を解いた時点で思うように点数が取れないのは、むしろ当たり前のことです。受験数ヶ月前の段階では、点数にこだわる必要はありません。受験本番で合格点が取れるように、過去問演習をしていくことになります。



難問は無理に解けるようにする必要はありません。解けなければいけない問題を得点できるようにするのは重要になってきます。
解きっぱなしにしない
丸つけは保護者または塾の先生が行い、間違えた問題はノートに解き直しを行います。過去問題集の解説を読んでも子どもでは理解できないものがあったり、解説が載っていないものもあります。塾で質問するなどしてノートにまとめ、あとで見返せるようにしておくことが大切です。間違えた問題の分析を行い、対策を立てていきましょう。
ある年度から問題の形式や傾向が変わる場合もあります。傾向が変わる前の古い問題は得必要がない場合もあります。説明会などであらかじめ教えてくれることもあるので要チェックです。
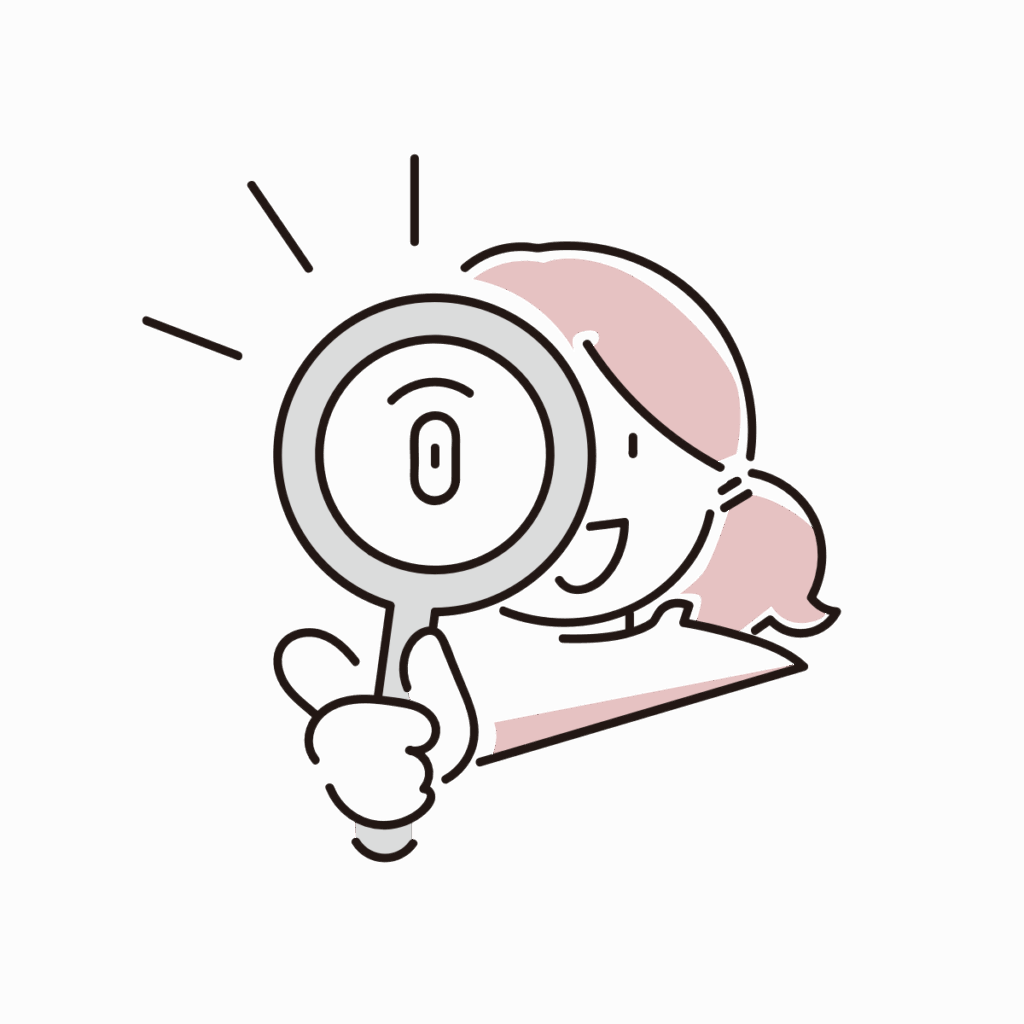
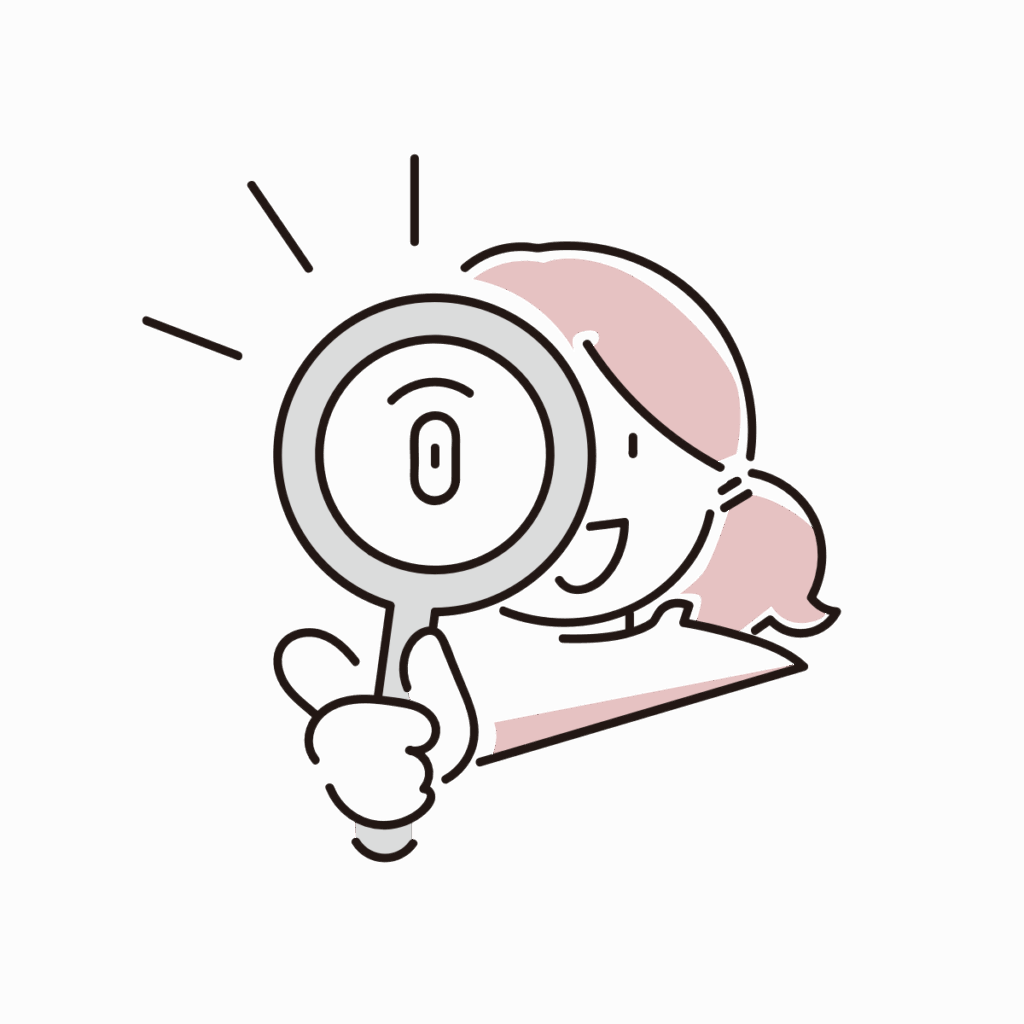
まとめ
過去問に取り組むことは、子どもにとても良い刺激になり受験生としての意識が高まります。過去問にポイント押さえて計画的に取り組むことで効果的な受験対策を行っていきましょう。
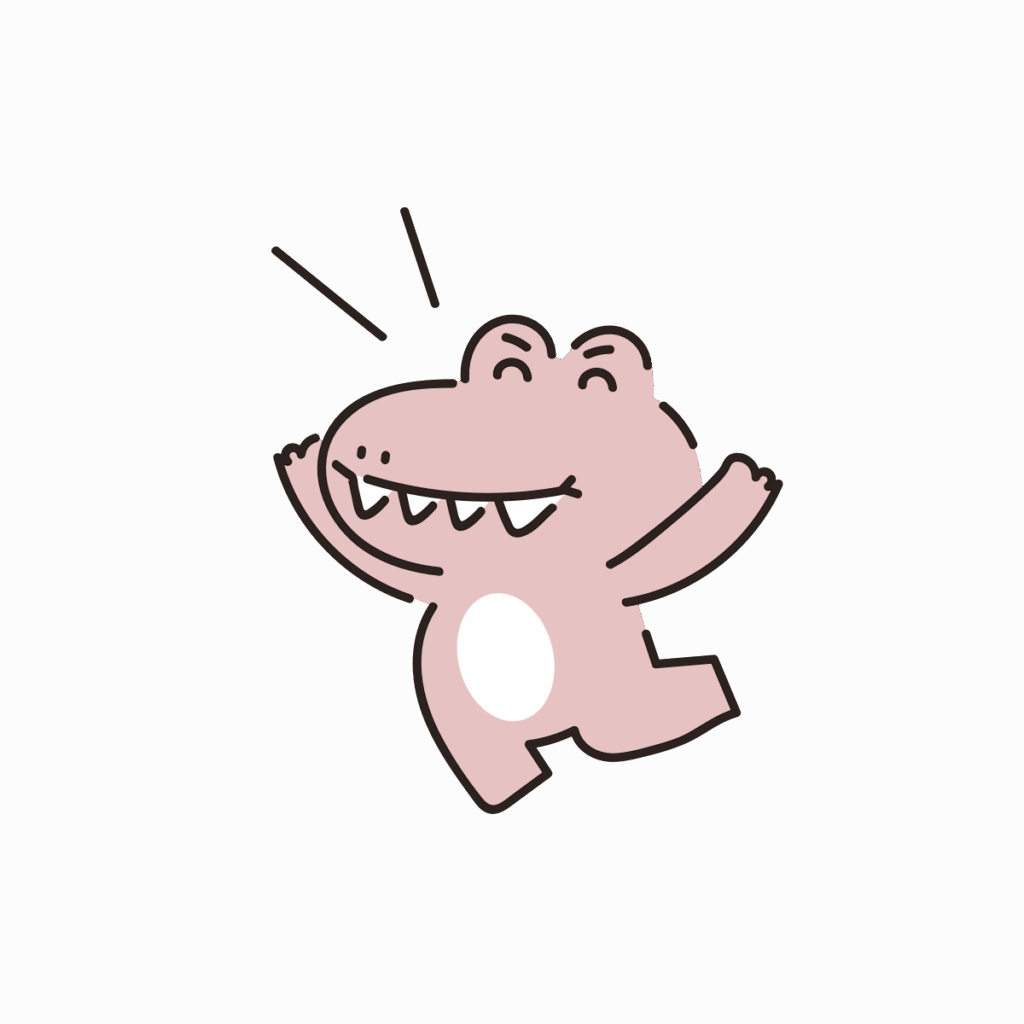
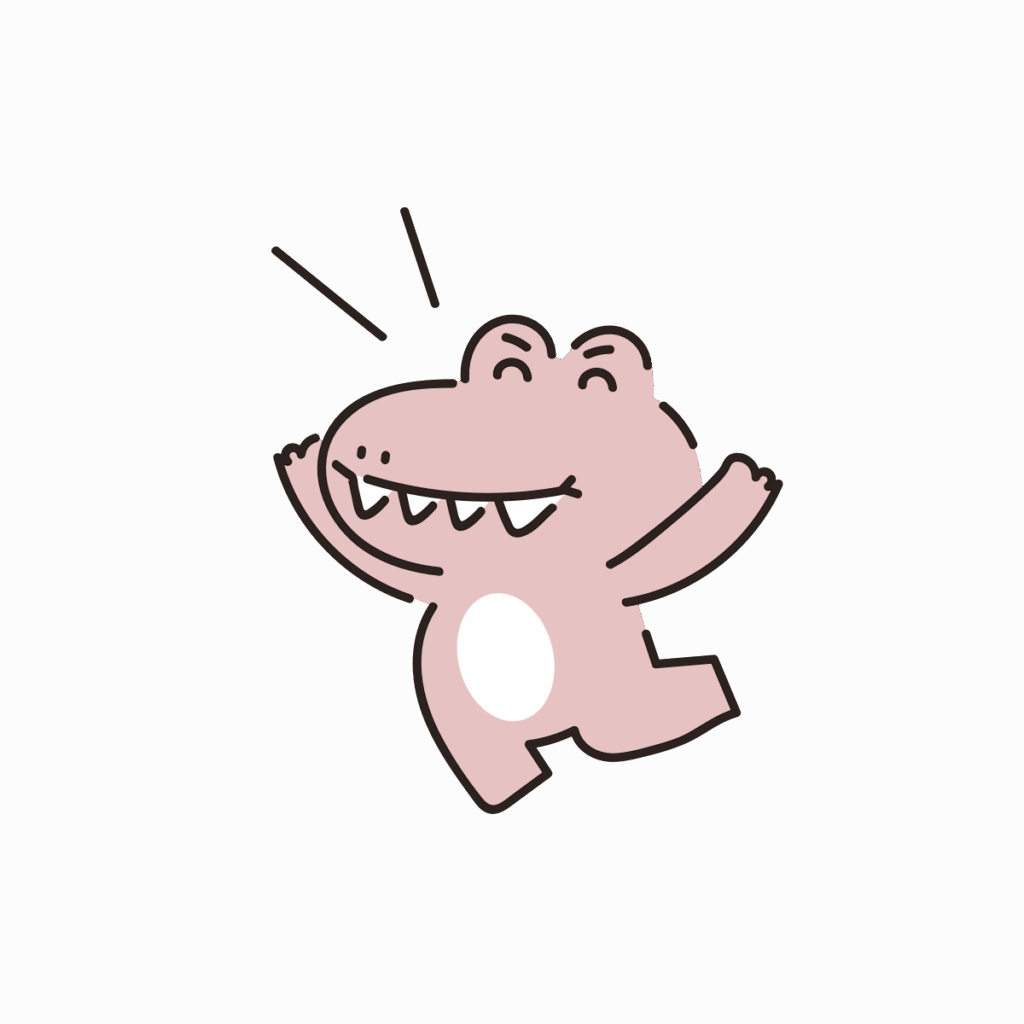
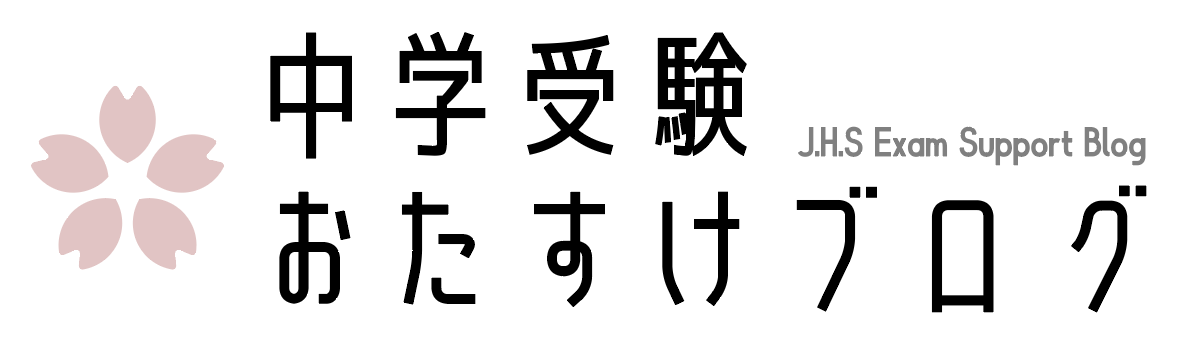
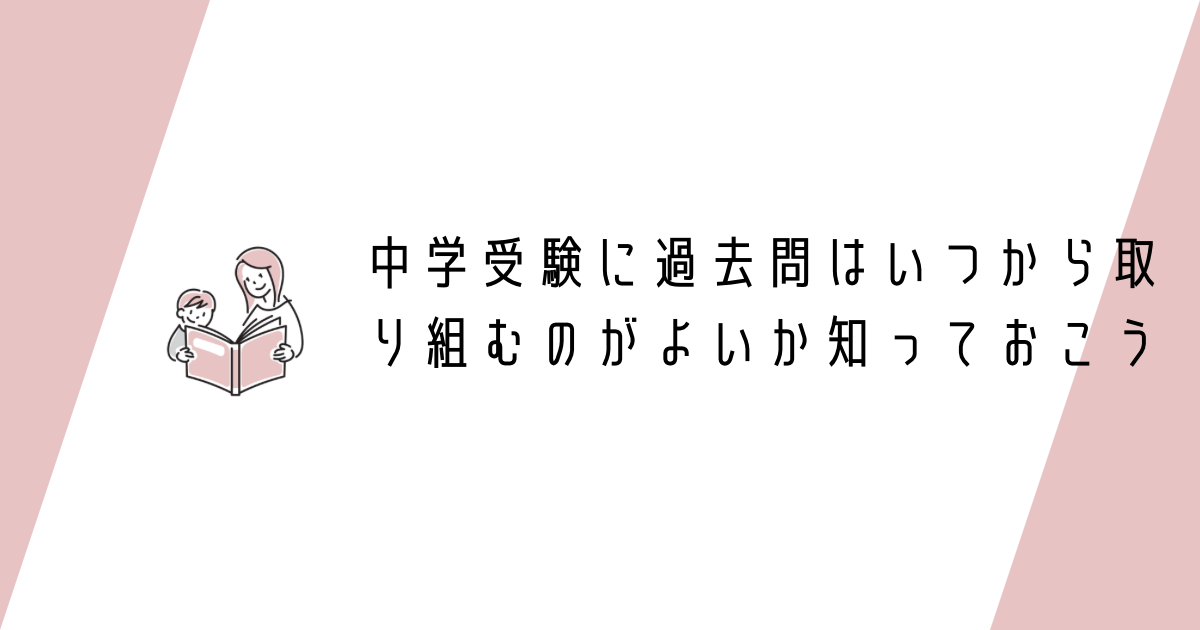

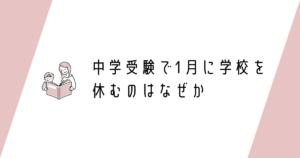

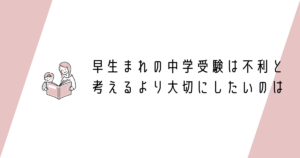
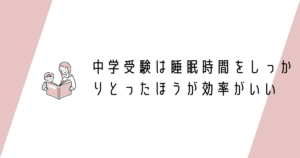
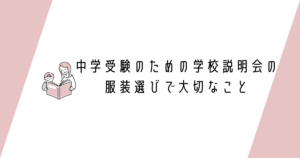
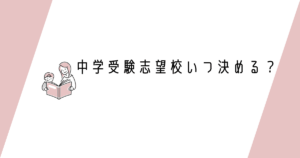
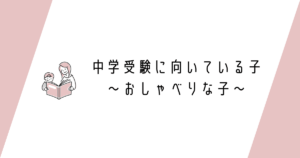
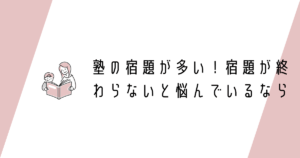
コメント