中学受験のために学習塾に通い始めると、「宿題が多い」という声はよく耳にします。
国語、算数、理科、社会の4教科の宿題が、1週間分または数日分の宿題がまとめて出されるため、量が多いと感じる原因なっているかもしれません。また、週2、3日通塾していると宿題が終わっていないのに次の宿題が出されることになるので、宿題に追われているように感じることもあるでしょう。
確かに、中学受験を目指す塾で出される宿題は、学校の宿題と比較するとかなり多いかもしれません。

考えてみて欲しいのは、本当に終わらせることができないほどの量であるか、ということです。
お子さんによって宿題をこなせる量に違いはあるかもしれませんが、工夫と考え方次第ではこなすことができるようになる場合もあります。
中学受験の塾の宿題が多い理由と、宿題をこなすためのコツをまとめています。


なぜ中学受験の塾の宿題は多いの?
塾では闇雲に宿題を出しているわけではなく、成績をあげるために必要だと思われる量を出します。テストの結果で塾のクラスが変わると宿題が変わるのは、そのためです。
塾の授業の時間は限られるので、広範囲の内容を学習するためインプットがメインにならざるを得ません。そのため、宿題でのアウトプットの宿題が必要不可欠になってきます。
成績をあげるために必要な宿題の量が多くなる理由としては、
- 授業内容の定着
- 家庭での学習習慣を身につける
- 思考力の育成
特に集団塾の場合は個別対応が難しいため、全員に同じ量の宿題を出すことになります。



宿題が多いという意見もありますが、宿題の量が少ないという意見もあるります。
多くの宿題をこなすには、お子さんに合わせた工夫が必要です。
塾さえ入っていれば成績が上がるというわけではありません。
宿題を終わらせるためのコツ
- 宿題の内容と量を把握する
- 1週間単位でスケジュールを立てる
- できにこだわりすぎない
1日に100個の英単語を覚えるのは大変だし、はじめから無理だと諦めたくなってしまうかもしれないけれど、1日10個ずつ10日間で覚えるなら頑張れそう!な気がしませんか?
目標が遠いと、やる気をなくして宿題をやってこなくなってしまう子も少なくありません。目標を近くに設定し、達成したら褒めてあげるを繰り返していくことがモチベーションの維持に繋げていきましょう。



宿題をやることは当たり前と言わずに、小さな目標を達成したことを褒めてあげて、やる気を引き出します。
宿題の内容を量を把握する
宿題の内容というのは、予習か復習か、基本か応用なのか、計算や漢字などの毎日やる必要がある宿題なのかということです。
宿題の内容の把握やスケジュール化は、お子さんだけでは難しいので保護者のサポートが必要になります。
保護者の方が忙しい場合は、ある程度はルーティン化しおいて、その時に宿題の内容よって割り振りをして行くと良いでしょう。
1週間単位でスケジュールをたてる
塾の宿題は次の塾の授業までに終わっていればいいわけですが、早めに終わらせようが遅めに終わらせようが、1つの教科の宿題を一回で終わらせるというやり方はおすすめできません。それは、数回に分けて同じ単元をやるほうが定着しやすいからです。
例えば、塾のつるかめ算の授業があった日につるかめ算の宿題を全て終わらせたとしても次の授業まで解き方を覚えているでしょうか?逆に、授業があった日につるかめ算の宿題をせずに、次の授業の前日に宿題をやろうとした時に、解き方を覚えているでしょうか?



定着させるには、少しずつで構わないので数回に分けて解くことが効果的です。
たまに「終わらせる」ことだけ考えて1週間分を1日で終わらせてくる子がいますが、それでは計算力や漢字力を身につけるという意味では効果が薄れてしまいます。
計算や漢字などの反復が必要なものは、毎日繰り返すことで力がついていきます。



やらないよりはいいかもしれないですが、せっかくやるなら効果的に力をつけたいですよね。
積み重ねが後々実を結びます!
計算や漢字は、受験直前になって慌ててもそのための学習時間を確保することは難しくなります。計算スピードや正確性は他の問題を解く上での基本になりますし、同様に漢字も他の教科でも正確に書くことが求められますし、入試では1点を争うことになるので大切な学習になります。
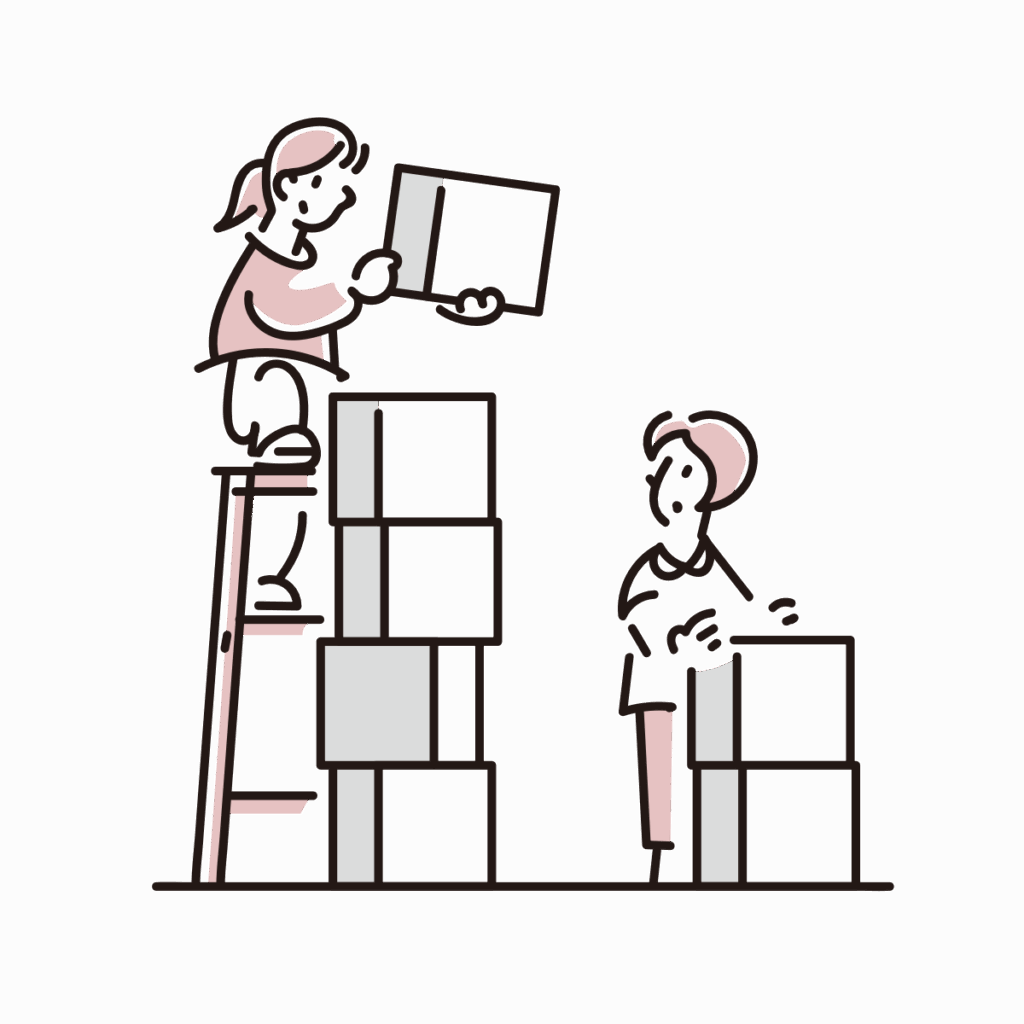
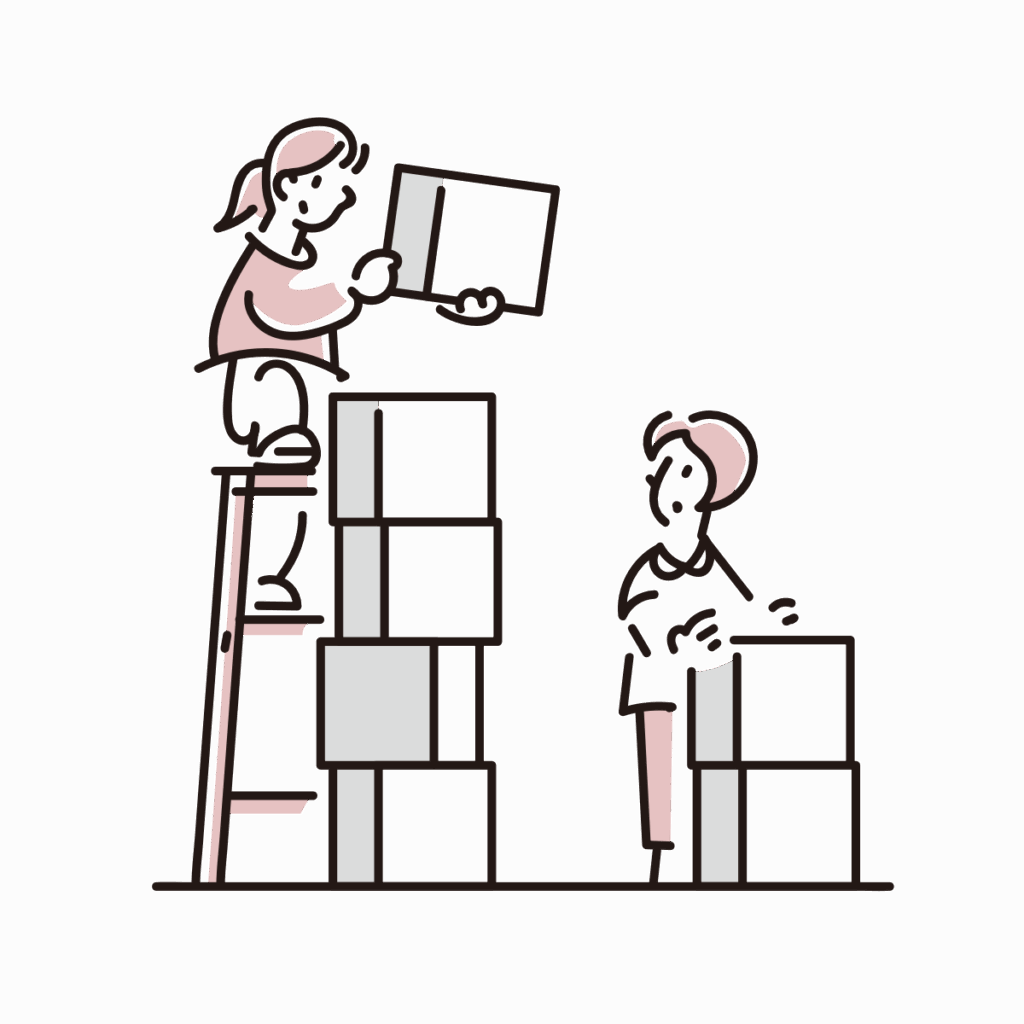
1回の学習時間を長くしすぎない
子どもの集中力は思うよりも短いです。集中力が切れている状態で学習を続けても効率が悪いので、この点においても1つの教科の宿題を数回に分けてやることが理想的です。食事や休憩、遊びを挟んで気分転換する時間も大切です。
宿題のできにこだわりすぎない
お子さんよって、宿題をこなすスピードや精度は異なってきます。全てできるようになるまでやらなければいけないと気負う必要はありません。まずは、基礎を定着させること、間違ったら直す、わからなかったら解き方を確認することを徹底し、基礎を定着させる、ことたくさんの問題に触れることを目的に、宿題をやっていきます。



基礎が身につくまでは、難しい問題はできなくても仕方がないです。
「この問題みたことある!」を目指しましょう!
基礎が身についてくれば、その子なりにスピードは上がってきますし、精度も上がってくるはずです。
塾で習ってきたからといって、宿題を全て1人で解けるようになっているとは限りません。わからないところは教えてあげてもいいですし、印をつけておいて塾で質問してくるようにするのも一つの方法です。
まとめ
塾のの宿題が多くて終わらないと悩んでいる方も多いことでしょう。宿題をこなしていくには、お子さんに合わせて工夫していくことが必要です。
全て完璧にしなければならない気負わずに、とりあえず終わらせることを目標にしていきましょう。どうしても終わらない場合は、塾の先生に相談して優先順位を決めてもらう、量を調節してもらうなどして、対応してみてください。
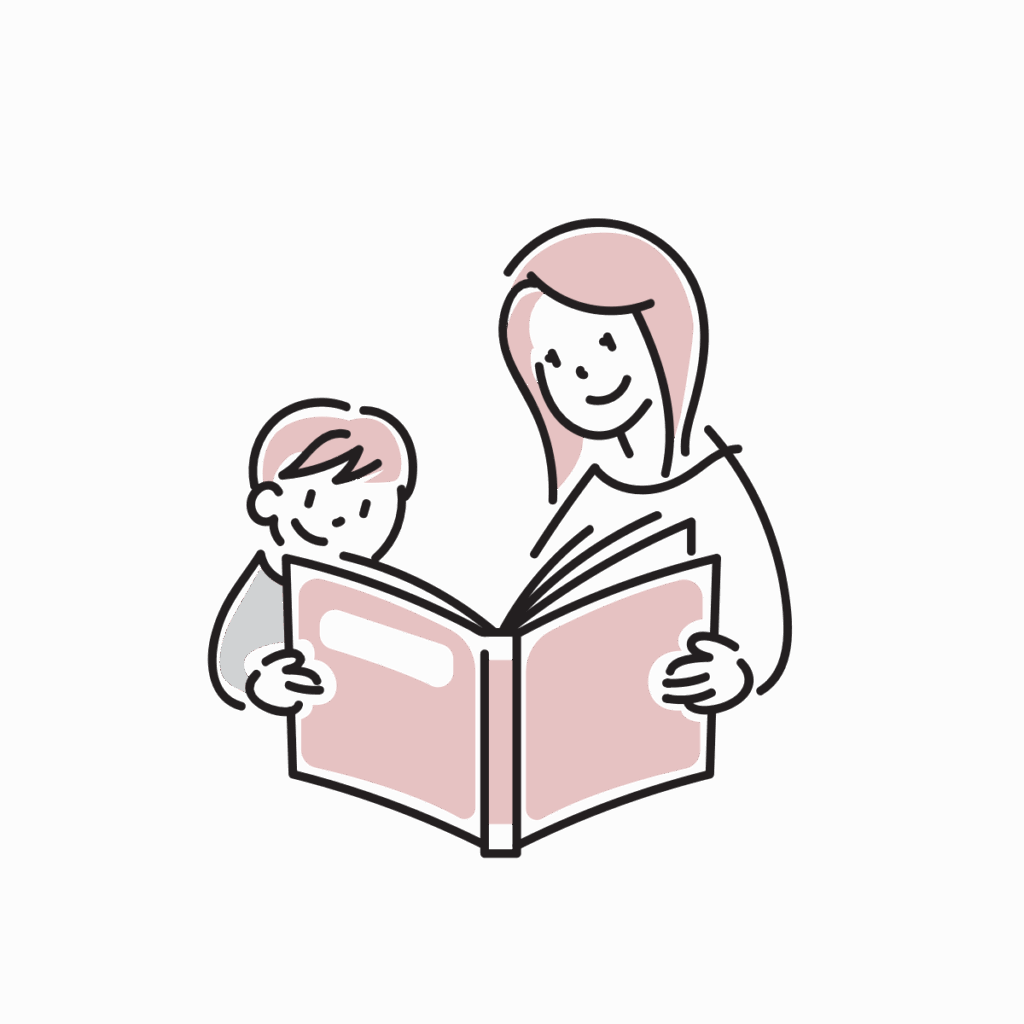
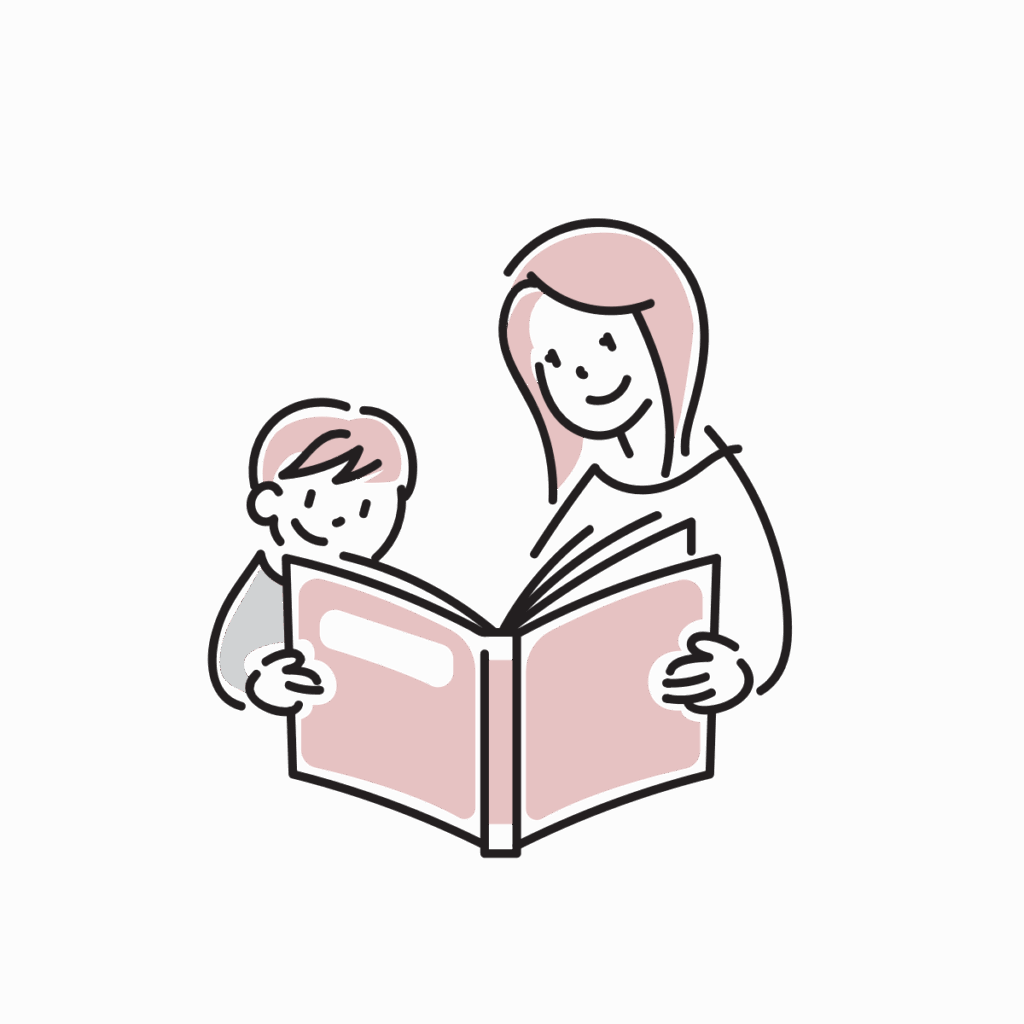
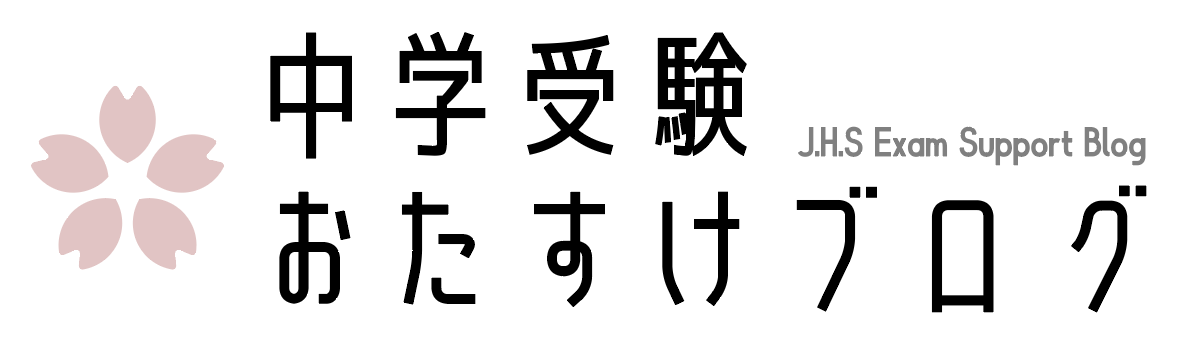
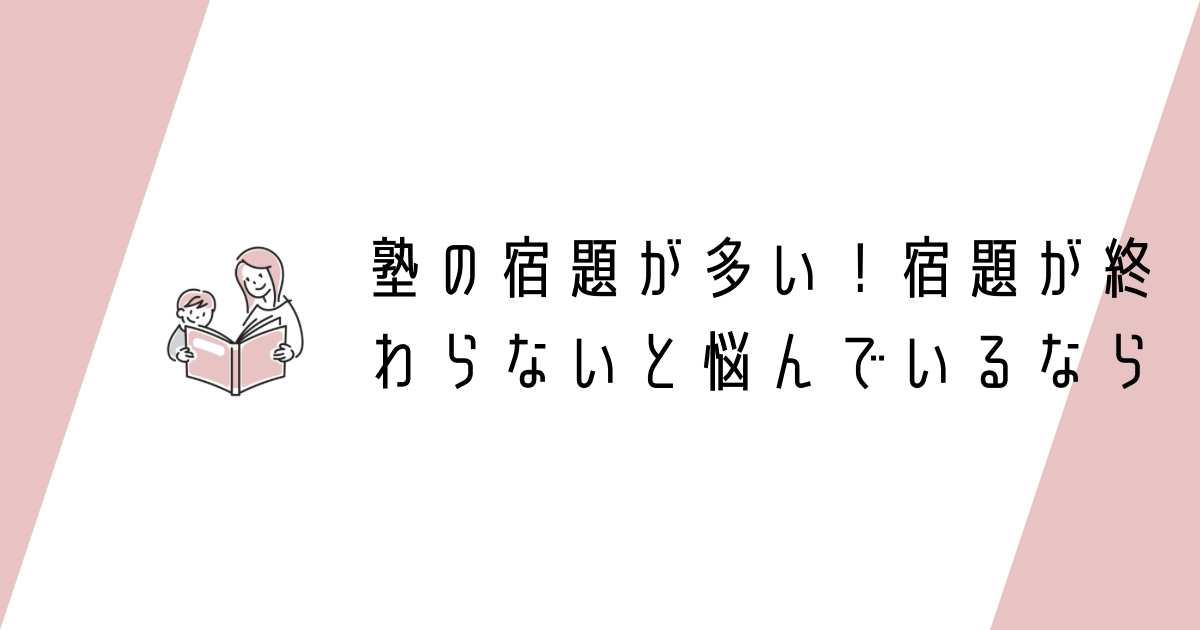
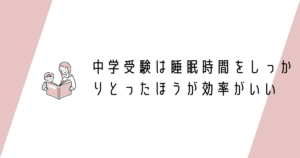
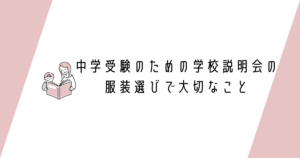
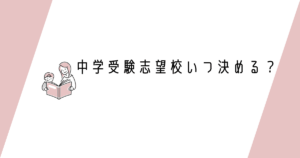
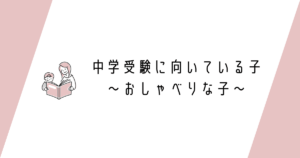
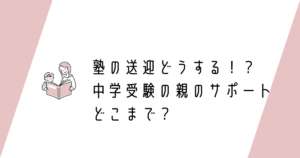
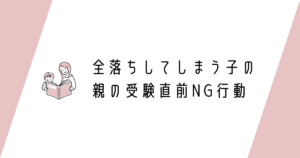
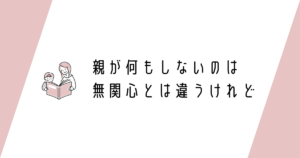
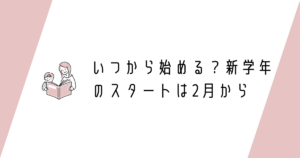
コメント